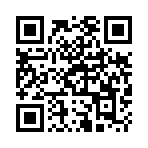2014年11月07日
木地師 諸星晃司さんのお礼参りの報告

水窪の奥にある木地師のお墓参りへ
山から山へ渡り歩いた木地師のお墓が各地の山に今も残っていて、お墓の後ろには16花弁の菊花紋が彫られているそうです。16花弁の菊花紋と言えば…そのことについてはいろんな説があるようですが、天皇や神社寺院への衣食住を調達する者は供御人、神人、供祭人、寄人などと称して体制側に取り込まれ平民の負担する年貢、公事、課役の免除と諸国往来中の特権を保障されていたと言う歴史があり、そのあたりが由縁でしょうか。

11月4日、先日個展を終えた諸星さんが「昨日水窪の奥の木地師のお墓へ無事個展が終了しました。ありがとうございました。とお礼参りに言って来たから」と写真を持って報告に来て下さいました。先人に感謝する心…その精神に感動してしまいますが、諸星さんは「当たり前のことだよ。」ときっぱり、確かに本来は何事もそうあるべきなのかも知れませんね。諸星さんは、このように気持ちの良い生き方をされていらっしゃいますが、それだけご自身の仕事に誇りをお持ちなのですね。
おまけ情報木地師に小椋、大蔵姓が多いのは…
木地氏の祖「惟喬親王」(844~897)が近江国小椋ノ庄(現在の滋賀県神埼郡永源寺町)でろくろによる木地政策の技法を開発し家臣の小椋大臣実秀と大蔵大臣惟仲にその技法を伝授したのが木地師の始まりと言われています。そのため現在も木地師には小椋、大蔵、小倉姓の人が多いと諸星さんが話して下さいました。
現在、小椋、大蔵の氏姓を名乗る木地師の末えいのみによって形成されている伝統の集落は「信州漆畑」だけだそうです。
山から山へ渡り歩いた木地師のお墓が各地の山に今も残っていて、お墓の後ろには16花弁の菊花紋が彫られているそうです。16花弁の菊花紋と言えば…そのことについてはいろんな説があるようですが、天皇や神社寺院への衣食住を調達する者は供御人、神人、供祭人、寄人などと称して体制側に取り込まれ平民の負担する年貢、公事、課役の免除と諸国往来中の特権を保障されていたと言う歴史があり、そのあたりが由縁でしょうか。

11月4日、先日個展を終えた諸星さんが「昨日水窪の奥の木地師のお墓へ無事個展が終了しました。ありがとうございました。とお礼参りに言って来たから」と写真を持って報告に来て下さいました。先人に感謝する心…その精神に感動してしまいますが、諸星さんは「当たり前のことだよ。」ときっぱり、確かに本来は何事もそうあるべきなのかも知れませんね。諸星さんは、このように気持ちの良い生き方をされていらっしゃいますが、それだけご自身の仕事に誇りをお持ちなのですね。
おまけ情報木地師に小椋、大蔵姓が多いのは…
木地氏の祖「惟喬親王」(844~897)が近江国小椋ノ庄(現在の滋賀県神埼郡永源寺町)でろくろによる木地政策の技法を開発し家臣の小椋大臣実秀と大蔵大臣惟仲にその技法を伝授したのが木地師の始まりと言われています。そのため現在も木地師には小椋、大蔵、小倉姓の人が多いと諸星さんが話して下さいました。
現在、小椋、大蔵の氏姓を名乗る木地師の末えいのみによって形成されている伝統の集落は「信州漆畑」だけだそうです。
Posted by 千代田画廊 at 11:12│Comments(0)